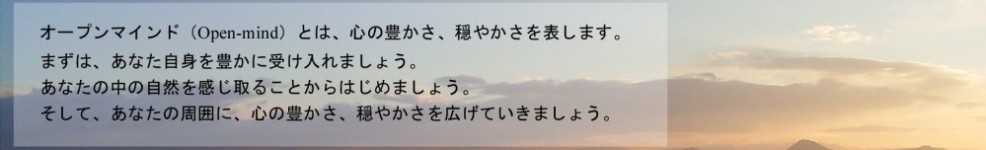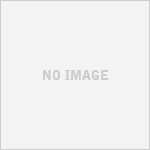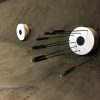にしゃんたさんのお母さん、お父さんの言葉から多文化共生の話まで
公開日:
:
et cetera
(一語一会)羽衣国際大学教授・タレント にしゃんたさん 母からの言葉http://digital.asahi.com/articles/DA3S12353583.html?rm=150
お母さんの言葉
~~~~~~~
「仏さまのご加護がありますから、あなたは絶対大丈夫」
「国籍が何であれ、私のせがれは私のせがれなんです」
(リンク先より引用)
~~~~~~~
以下のような理由から、自分で日本の中古車を買って近所に自慢したお父さん
~~~~~~~
スリランカでいちばんわかりやすい親孝行は、日本の中古車を贈ることなんです
(リンク先より引用)
~~~~~~~
多文化共生についての視点
~~~~~~~
日本は少数者に対して優しい社会とはいえず、多数者だけが笑っている。多数者も、少数者も、共に笑える社会こそ共生のあるべき姿だと信じている。
(リンク先より引用)
~~~~~~~
以上、すべて素敵な言葉でした。
--------
「多文化共生」について。
先日記事にした、「何を笑うか」というテーマと同じです。
「笑い」で何を笑っているかを見ると、私たちのレベルがわかる http://views.core-infinity.jp/2016/05/laugh/
多文化共生って、にしゃんたさんの言葉がすべてだなあ。
少数だからって、弱者じゃないし、
弱者だからって、大目に見てもらったり、庇護されなきゃならないものじゃないし、
弱者に認定されないために、多数側に行こうともがくものでもないし。
少数者、弱者であれば、同等の活動ができるような状況を作ってもらう必要はあるし、
もしそれが現金的な補償だったら、それに胡坐をかいている場合じゃないし。
その人、
その文化、
その考え方
その生き方
がそのまま尊重されて、対等に対話できることが必要。
それは、少数者のためのものじゃなく、
多数者のためのものでもなく、
顔と名前と声がある、
私たち一人一人ための
私たち一人一人が自立していけるために必要なこと。
それは、多様性を確保していることになるし、
社会としても強いといえる。
だからこそ、にしゃんたさんの
「多数者も、少数者も、ともに笑える社会」
という言葉は本質を突いている。
関連記事
-

-
「おまえのことが大切だからさ」を最初に伝える
> 地球では『以心伝心』は無い前提で、 > こんな風に話すんですよ。 > > (4)「おま
-

-
才能はわかりやすい?
ロクの世界(予告編) ~~~~~~~ 真の才能は「狂気に満ちた集中」から生まれるIT
-

-
人はなぜ子供を持ちたいか?
つい先日、Facebookにこんなことを書いた。 「子供をなぜ持つのだろうか?」 子供を
-

-
「あ、私は生きてていいんだ」
自分に自信のない人へ。自信がないのは、自分に能力や実績がないからではない。どんなに結果を出している人
-

-
愛があるなら、すぐ忘れられる存在になること、自分がやりたいことをすること
そこそこ前に上司が急死しまして、ここ暫くは残った仕事の引き継ぎや片付けをやっているのですが、解ったこ
-

-
愛の証拠や手順、ポイントカードはない
> 人は、利己心が相手の中にまるで見えない時にも、自分が本当に愛されているかどうかを、深刻に思い悩む
-

-
「誰かに褒めてもらえたら、その人の言葉、ちゃんと聞く様にしてください。」
『誰かに褒めてもらえたら、その人の言葉、ちゃんと聞く様にしてください。適材適所、生きやすくなりますよ
-

-
蜷川幸雄さんに降りてきたメッセージ
大竹しのぶさんのこのような記事がありました。 (大竹しのぶ まあいいか:122)涙が、止まらな
PREV :
「前者・後者」探求がさらに進化・深化していることを見て
NEXT :
人はなぜ子供を持ちたいか?